小松菜(コマツナ)は栄養豊富な野菜ひとつで、
カルシウム、カリウム、鉄分、ビタミンC、βカロテンなどの栄養を含み離乳食などでも人気の食材となります。
また、初心者でも栽培しやすいため家庭菜園などでもおすすめの野菜です。
そんな小松菜(コマツナ)の基本情報や種まきからプランターで栽培する方法をご紹介します。
小松菜(コマツナ)の基本情報
別名:冬菜
科名・属名:アブラナ科アブラナ属
学名:Brassica rapa var. perviridis
種まき時期:3月~6月(春まき)、9月~10月(秋まき)
植え付け時期:4月~7月(春まき)、10月~11月(秋まき)
収穫時期:5月~9月(春まき)、11月~3月(秋まき)
主な病気:白さび病 など
主な害虫:アブラムシ、ヨトウムシ など
一般的に小松菜の旬は秋から冬とされており、秋に種まきを行い冬に収穫する品種が多くあります。
冬の寒さの中で育つことで、葉っぱの厚みが増し、柔らかく甘みのあるおいしい小松菜に成長しますよ。
適した環境

土
種まき2週間前:苦土石灰をまいて良く耕す
種まき1秋雨間前:化成肥料を追肥する
プランターで栽培する場合、野菜専用の培養土を使用すると良いでしょう。
おすすめの培養土
「ハイポネックス 野菜の培養土」

日当り
日当たりの良い場所を好みます。
日当たりが不足すると葉っぱの色が悪くなったりと、上手く育たない場合があります。
しかし、夏場の強い直射日光は、葉っぱが焼けてしまう原因にもなります。
もし可能であれば、午前中はしっかりと日当たりの良い場所で栽培し、
午後は日陰に移すようにすると良いでしょう。
プランターで栽培する場合、移動が楽で良いですね。
プランターでの栽培方法

用意するもの
・プランター(深さが20cm以上のもの)
・種
・野菜用培養土
・化成肥料
・鉢底石
・移植ゴテ
・選定ばさみ
・防虫ネット
プランターでの種まき
プランターに底が見えなくなるほど鉢底石を敷き、その上に野菜用培養土を入れます。
土を入れる量は、プランターの縁から2cmほど高さは残しておきましょう。
深さ1cmほどの溝を作り、1cm間隔で種をまきます。
幅は15cmほどあけておきましょう。
土を薄くかぶせて軽く押さえましょう。
プランターは日当たりの良い場所に置き、発芽までは毎日水やりを行います。
種まき後、3〜4日くらいで発芽します。
発芽した後は、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりを行いましょう。
また、春から夏にかけてはアブラムシなどの害虫に注意が必要です。
防虫ネットを被せるなど対策を行いましょう。
おすすめのプランター
「アップルウェアー クイーンプランター 650型」

間引き
発芽し、双葉が開いたタイミングで最初の間引きを行います。
株間が3cmほどになるように間引きを行います。
しっかりと成長している株を残し、育ちの悪い株を間引くようにしましょう。
間引き後は土寄せを行なってください。
土寄せ
株元に土を寄せる作業のことを言います。
倒れたりしないようにするためでもありますが、
根っこがしっかりと張るように、乾燥しないように作業をしておくと良いでしょう。
本葉が7〜8枚ほどになったら、1本おきに株の根元を選定ばさみでカットします。
追肥
最初の間引きを行った1週間後に最初の追肥を行いましょう。
化成肥料を10〜20gほどの量をまきます。
その後は2週間に1回の追肥を行いましょう。
おすすめの化成肥料
「住友化学園芸 マイガーデン ベジフル」

育て方のポイント

水やり
水やり
種まき時期から発芽するまでは土が乾燥しないよう、こまめに水やりを行いましょう。
ただし、種が流れてしまわないようにやさしく水やりを行う必要があります。
芽が出てからは土の表面が乾いたら水をやる程度で問題ないです。
乾燥には強い野菜なので、水やりのしすぎは根腐れなどを起こす可能性があります。
また、プランター栽培の場合、受け皿に水が溜まっているのも危険です。
よく観察して水やりを行ってくださいね。
肥料
プランター栽培で市販の培養土を使用する場合は、元肥をする必要はありません。
追肥のタイミングは間引きの1週間後と、
その後2~3週間おきに追肥を行いましょう。
病害虫
白さび病とは、茎や葉っぱなどに白っぽく病斑が出る病気です。
天候不順が続くと起こりやすく、カビが原因となります。
空気伝染してしまうため、見つけ次第育てている場所以外で処分しましょう。
アブラムシやアオムシなど見つけた場合は取り除き、
それでも発生してしまう場合は殺虫剤を散布して対策を行いましょう。
収穫
草丈が25cmほどになったら順次収穫を行いましょう。
間引きと同様に株の根元を選定ばさみでカットするか
手で株ごと引き抜いて収穫しましょう。
おすすめの選定ばさみ
「CHIKAMASA 摘花・野菜鋏」

鉄分、カルシウム、ビタミンなどを多く含む小松菜は
離乳食初期から積極的に食事に加えたい食材の一つです。
お子さんと一緒に栽培から料理まで楽しんでみませんか?






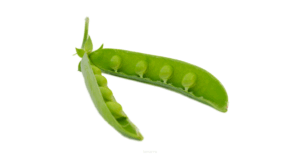


コメント